Special Feature
ユーザーの行動データは宝の山 プロダクトアナリティクスが導くDXの次のステージ
2021/08/23 09:00
週刊BCN 2021年08月23日vol.1887掲載
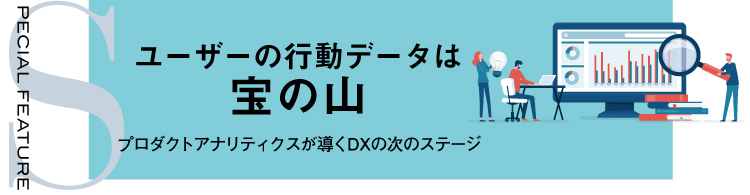
2011年、起業家のマーク・アンドリーセン氏が「Software is Eating the World(ソフトウェアが世界を飲み込む)」と指摘し、あらゆるビジネスがソフトウェア化する未来を予測した。その言葉通り、ウーバー、エアビーアンドビー、フェイスブック、スポティファイ、ネットフリックスなど、デジタルプロダクトを扱う多くの企業が「デジタルディスラプター」となり、既存市場を大きく変えた。その成長の背景には「プロダクトアナリティクス」によるユーザーの行動解析がある。21年にはプロダクトアナリティクスツールを手掛ける2社が国内市場に本格参入した。国内ではまだ聞きなれないプロダクトアナリティクスだが、もはや一部の先進企業だけのものでなはい。
(取材・文/冨永裕子 編集/藤岡 堯)
ビジネスの成長に効くユーザー体験の向上
プロダクトアナリティクスとは、顧客の行動データを収集し、その分析からインサイトを得るための手法だ。そのためのツールは、「データの収集」と「データの分析」という二つのコア機能で構成され、企業は集めたデータの分析から得た洞察をプロダクト改良のための意思決定に役立てることができる。
行動データの収集対象となる「顧客」とは「ユーザー」を意味する。従来、エンドユーザーのニーズ把握は主にインタビューによる聞き取りが一般的だった。しかし、この方法で得られるデータは必ずしも正確ではない。ユーザーがどのような機能を使い、操作のどの部分でつまずいたかなど、細部を把握するまでには至らず、声の大きい一部のユーザーの意見が目立ってしまい、陰に潜む重大な要望を反映できないおそれもあるからだ。
プロダクトアナリティクスはこの課題を解決する方法であり、ソフトウェアの使い方に関する問題をデータで解決するアプローチとも言える。行動データであれば誰かの主観が入る余地は少なく、ユーザー全員から取得できる。一定のデータ量が必要になるものの、これまでの調査手法では難しかった客観的な分析が可能になる。
プロダクトアナリティクスを活用できる領域は広い。社内の情報システムはもちろん、ソフトウェアビジネスを展開しているSaaSベンダー、コンシューマー向けにデジタルサービスを手掛ける企業、ECサイトの運営事業者、IoTデバイスを提供するメーカーも、宝の山であるユーザーの行動データを生かすことができる。プロダクトの使われ方を分析して得たインサイトを、ユーザー体験(UX)の向上に役立て、ビジネス成長につなぐことも期待できる。
今後の需要拡大を見据え、日本市場に進出した米アンプリチュードと米ペンドのビジネス戦略から、プロダクトアナリティクスの可能性を探る。
アンプリチュード
ヘビーユーザーのニーズの理解に貢献 製品のローカライズを推進
アンプリチュードはMIT出身のスペンサー・スケイツ氏とカーティス・リュー氏の二人が12年に創業し、「Help Companies Build Better Products(企業がより良いプロダクト開発を行えるよう支援すること)」をミッションに掲げる。日本法人の設立は21年3月で、製品のローカライズを着々と進めている。グローバルでは4万のデジタルプロダクトの裏側でアンプリチュードの製品が稼働中だ。導入企業はスタートアップからFortune 100の大企業まで規模を問わない。テクノロジー企業ではシスコシステムズやIBM、SaaSベンダーではアトラシアンやハブスポットが利用しているほか、ストリーミングサービスやD2C(Direct to Consumer)ブランドなども導入している。ユーザー層はプロダクトマネージャーとエンジニアが主で、マーケティング、IT部門、エグゼクティブが直接使う場合もある。アンプリチュードでは、ユーザーを「新規」「定着」「復帰」「休眠」の四つに分類して分析できるようにしており、習熟したユーザーや離脱の兆候があるユーザーなどの数を把握できる。
全てのユーザーを一律に扱っていては、ヘビーユーザーの不満を見落とし、ユーザーが定着しない。プロダクトを洗練させるときの意思決定では、ヘビーユーザーの行動への着目が重要となる。
「マジックナンバー」でPay Wallを突破
日本法人の米田匡克カントリーマネージャーはアンプリチュードの強みについて、「すぐに使える14種類のチャートを提供していること」と話す。一口にユーザーの行動を分析すると言っても、どこから手をつけていいかわからないこともある。しかし、事前定義済みのチャートがあれば、先進企業がビジネス成長のために実践しているベストプラクティスを参照できる。特にユニークなチャートが「マジックナンバー抽出」だ。マジックナンバーとは、「特定のアクションを規定回数(時間)以上行う」ことでサービスの継続率や収益などの重要指標が向上する数字を指す。

デジタルサービス運営企業にとって、無料ユーザーに「Pay Wall(支払いの壁)」を越えさせ、有料ユーザーとすることは、ビジネスを成長させる上で避けて通れない。Pay Wallの一例が「Zoomの40分」だ。Zoomは無料でも使えるが、ミーティングが40分を超えると有料プランを勧められる。この「40分」がZoomのマジックナンバーと言えよう。アンプリチュードは、顧客が自分たちのプロダクト成長にとっての「40分」が何かを見つけるために、またユーザージャーニーや新機能リリース後の反響を分析するチャートなどもそろえている。
データ分析からインサイトを得られても、放置していては意味がない。プロダクト改良という実践の機会が多いほど、市場からの評価が高まる。そこで重要なのはテストだ。プロダクトアナリティクス先進企業の場合、テストを年間1000回以上実施していることも珍しくないという。アンプリチュードは「Amplitude Analytics」のほか、UXパーソナライゼーションのための「Amplitude Recommend」、テスト自動化のための「Amplitude Experiment」を統合的に提供し、企業のプロダクト体験をより良いものにする取り組みを進めていく計画だ。
さらに米田カントリーマネージャーは「パートナーも開拓していきたい」と意気込む。大手ITベンダーにはソリューションパートナーとしての役割を期待しているという。今後はデータマネジメントの領域でプロダクトアナリティクスに取り組む企業を支援していく方針だ。
ペンド
分析と定着の2本柱でDX支援「プロダクト主導」を追求
どちらかというと、一般消費者が使うデジタルサービスのマネタイズと体験価値の向上に焦点を当てた製品を提供するアンプリチュードに対し、社内ユーザーが使うビジネスアプリケーションの使いやすさと定着を重視しているのがペンドである。ペンドは、創業者兼CEOのトッド・オルソン氏がプロダクトマネージャーとしての自ら経験を基に、13年に設立した会社だ。日本法人の設立はアンプリチュードと同じ21年3月。導入しているテクノロジー企業には、アドビ、シスコシステムズ、シトリックス、インフォア、レッドハット、ゼンデスクなどが名を連ねる。同社のビジョンは「企業のプロダクト主導への変革を支援すること」。この「プロダクト主導」とは、プロダクトを中心にビジネスの成長を考えることをいう。とはいえ、プロダクトアウトで顧客ニーズを無視してビジネスを展開するわけではない。デジタル時代のプロダクトとは、顧客とのコミュニケーションツールでもある。ベンド・ジャパンの高山清光カントリーマネージャーは「本当の意味で顧客に向き合うためにはプロダクトのデータを見て、意思決定のできる組織を作ることが重要であり、それがプロダクト主導の本質」と解説する。

ペンドのターゲット顧客は大きく二つに分けられる。一つはSaaSベンダーのように、自社で開発したデジタルプロダクトでビジネスを行う企業のプロダクトマネージャー、もう一方はDXに取り組む企業のDX専門組織やIT部門のリーダーである。
ベンター、ユーザー企業双方をサポート
企業がビジネスで使うアプリケーションの分野は、SaaSが第一の選択肢として定着しつつある。サブスクリプション型のビジネスモデルを採用している企業にとっての重要な成功要因は、ユーザーにできるだけ長く使い続けてもらうことだ。一方、SaaSを使う企業にとっては現場への定着が課題になる。SaaS導入が進めば、社員1人当たりのコストも積み重なる。費用に見合った使い方ができているかがシビアに問われる。十分に使いこなせていない場合は、IT部門は利用を促すサポートを提供しなくてはならない。
ペンドがユニークなのは、プロダクトアナリティクスと同じ環境でユーザー定着のための機能も提供している点だ。具体的にはユーザーが操作中に「ガイド」を表示できる。高山カントリーマネージャーは「分析からインサイトを得て、定着化のための施策をすぐに実行に移せる」と強調する。そのインサイトを得る際、定量データと定性データの両方を使うのもペンドの特徴だ。前者はユーザー行動に関するあらゆるイベント、後者ではNPS(Net Promoter Score)とフィードバックが使えるという。
高山カントリーマネージャーはペンドの強みとして次の3点を挙げる。第1にガイドの表示を、設定ベースの「ローコード・ノーコード」でできることだ。第2はセグメント単位でガイドの表示ができること。初心者には丁寧なガイド、習熟者向けにはシンプルなガイドを、出し分けできる。最後が遡及分析(Retroactive Analytics)と呼ばれるテクノロジーである。ペンドでは、問題が分かった時点から遡り、過去のデータを分析に使えるようにしている。
販売戦略では直販だけではなく、パートナー販売も重視。今後、IT部門に太いパイプを持つSIerのビジネスのサポートを強化する考えだ。
デジタルプロダクトを巡っては、ユーザーエンゲージメントを高めることがますます重要になってくる。そのためには、顧客がプロダクト内でいかに期待する価値が得られたかを測定する仕組みづくりが求められる。プロダクトアナリティクスを使うことで、「宝の山」であるユーザーの行動データからサクセスにつながる指標をつかむ。国内でも今後、このような取り組みが浸透していきそうだ。
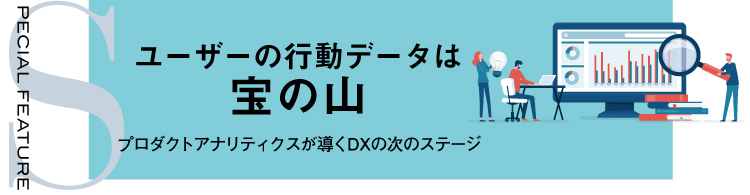
2011年、起業家のマーク・アンドリーセン氏が「Software is Eating the World(ソフトウェアが世界を飲み込む)」と指摘し、あらゆるビジネスがソフトウェア化する未来を予測した。その言葉通り、ウーバー、エアビーアンドビー、フェイスブック、スポティファイ、ネットフリックスなど、デジタルプロダクトを扱う多くの企業が「デジタルディスラプター」となり、既存市場を大きく変えた。その成長の背景には「プロダクトアナリティクス」によるユーザーの行動解析がある。21年にはプロダクトアナリティクスツールを手掛ける2社が国内市場に本格参入した。国内ではまだ聞きなれないプロダクトアナリティクスだが、もはや一部の先進企業だけのものでなはい。
(取材・文/冨永裕子 編集/藤岡 堯)
ビジネスの成長に効くユーザー体験の向上
プロダクトアナリティクスとは、顧客の行動データを収集し、その分析からインサイトを得るための手法だ。そのためのツールは、「データの収集」と「データの分析」という二つのコア機能で構成され、企業は集めたデータの分析から得た洞察をプロダクト改良のための意思決定に役立てることができる。
行動データの収集対象となる「顧客」とは「ユーザー」を意味する。従来、エンドユーザーのニーズ把握は主にインタビューによる聞き取りが一般的だった。しかし、この方法で得られるデータは必ずしも正確ではない。ユーザーがどのような機能を使い、操作のどの部分でつまずいたかなど、細部を把握するまでには至らず、声の大きい一部のユーザーの意見が目立ってしまい、陰に潜む重大な要望を反映できないおそれもあるからだ。
プロダクトアナリティクスはこの課題を解決する方法であり、ソフトウェアの使い方に関する問題をデータで解決するアプローチとも言える。行動データであれば誰かの主観が入る余地は少なく、ユーザー全員から取得できる。一定のデータ量が必要になるものの、これまでの調査手法では難しかった客観的な分析が可能になる。
プロダクトアナリティクスを活用できる領域は広い。社内の情報システムはもちろん、ソフトウェアビジネスを展開しているSaaSベンダー、コンシューマー向けにデジタルサービスを手掛ける企業、ECサイトの運営事業者、IoTデバイスを提供するメーカーも、宝の山であるユーザーの行動データを生かすことができる。プロダクトの使われ方を分析して得たインサイトを、ユーザー体験(UX)の向上に役立て、ビジネス成長につなぐことも期待できる。
今後の需要拡大を見据え、日本市場に進出した米アンプリチュードと米ペンドのビジネス戦略から、プロダクトアナリティクスの可能性を探る。
続きは「週刊BCN+会員」のみ
ご覧になれます。
(登録無料:所要時間1分程度)
新規会員登録はこちら(登録無料) ログイン会員特典
- 注目のキーパーソンへのインタビューや市場を深掘りした解説・特集など毎週更新される会員限定記事が読み放題!
- メールマガジンを毎日配信(土日祝をのぞく)
- イベント・セミナー情報の告知が可能(登録および更新)
SIerをはじめ、ITベンダーが読者の多くを占める「週刊BCN+」が集客をサポートします。 - 企業向けIT製品の導入事例情報の詳細PDFデータを何件でもダウンロードし放題!…etc…
- 1



















