監査法人や公認会計士で組織する財団法人財務会計基準機構が先に公表した「ソフトウェア取引の収益の会計処理に関する実務上の取扱い(案)」(実務対応報告公開草案第20号)が波紋を呼んでいる。同機構によると「ソフトウェア取引における架空売上や利益転化といった不正行為を防止し、企業経営の透明性を高めるのが目的」で、早ければ今年4月から株式公開企業に適用、来年4月に同規定への準拠が義務づけられる。現在は草案に対する意見を広く募集している段階で詳細は未定だが、規定適用は既定の路線で「懸案は実施時期だけ」という。ソフト取引の何がどう変わるのか。(佃均(ジャーナリスト)●取材/文)
明確な契約と収益の透明化を規定
財務会計基準機構がソフトウェア取引における収益の会計処理の問題に本腰を入れるようになったきっかけは、東証マザーズに上場していたアソシエント・テクノロジーの不正経理だった。架空取引による粉飾決算が発覚し、同社は上場廃止に追い込まれた。その後もメディア・リンクスが同様の理由で上場廃止となり、今年に入ってライブドア事件が起こった。「IT関連企業」というだけで実態とかけ離れた株価がつき、時価総額経営の歪みを肥大化させたのは、取引と収益の不透明さが一因ではないか、というわけだ。
■丸投げ案件は、売上高から除外することに 草案の最大のポイントは、ソフト開発業務の多重取引における収益認識に一定の指針を示したことだ。原文には、「物理的にも機能的にも付加価値の増加を伴わず、会社の帳簿上通過するだけの取引も存在する。このような複数の企業を介する情報サービス産業におけるソフトウェア関連取引において、委託販売において手数料収入のみを得ることを目的とする取引の代理人のように、一連の営業過程における仕入及び販売に関して通常負担すべきさまざまなリスク(瑕疵担保、在庫リスクや信用リスクなど)を負っていない場合には、収益の総額表示は適切でないと考えられる」とある。
一言でいえば「外注に丸投げした案件は、取扱高ではあるけれど、決算上の売上高に入れてはダメですよ」ということになる。システム開発案件の受注で上位に位置する企業が多く加盟している情報サービス産業協会は、草案検討委員会に参加しているが目下のところ「静観」の構え。売上高に占める外注比率が3割を超えていたり、親会社の案件を外部に発注するだけの企業も少なくない。「業界健全化のため歓迎すべき指針」という声がある一方、「身内の恥」を自ら語るには勇気が要るという意見もある。
発注元であるユーザー企業にとっても痛し痒しだ。一つは「ソフトウェアは無形の資産」と既定されているため、これまで外注の人件費、つまり経費で処理していた対価を資産として計上しなければならなくなる。
さらに、契約内容を明確にするには、システムの仕様を厳密に詰めていくことが要求されるのも厄介だ。機能や性能ばかりでなく、安全性や品質など、従来は数値化されなかった部分をどのように評価するかも課題となる。
■分割検収や複合取引に指針が示される 実務取扱案では、コンピュータ・プログラムとシステム仕様書、フローチャートなど関連文書について、市場販売目的受注制作の2形態をあげ、その関連業務を含め契約の形式にかかわらず対象範囲に規定している。またソフトウェア取引と関連業務の特徴について、無形資産であること、取引が高度化・多様化していることをあげ、収益認識複合取引総額表示の3項目に論点を絞った。
収益認識に関して、以下にあげるようなケースは「一般的に、事実の存在について疑義が生じる」としている
・当該取引に関する契約書等につき、ドラフトしか存在していない
・パートナー(協力会社)に取引を仲介させている
・検収書またはこれに類似するものが入手されていない
・検収書またはこれに類似するものが入手されているにもかかわらず、入金予定日を過ぎても入金がない、もしくはソフトウェアの主要な機能に関するバグの発生等により作業を継続している
・売上計上後に顧客への多額の返金または大幅な値引きが見込まれている。もしくは類似の取引で過去においてそのようなケースが多く発生している
開発プロジェクトをいくつかのフェーズに分け、フェーズごとに契約・検収する分割検収については、「各フェーズ完了後において、売上金額の事後的な修正が行われることがある」とし、「各フェーズ完了時の対価の成立、販売代金の回収可能性、返金の可能性等、資金回収のリスクを考慮する必要がある」とした。
また機器やサービスなど異なる取引を同一の契約書で結ぶ複合取引については「個々の販売時点が異なっているにもかかわらず、一方の財の販売時に他方の財の収益を同時に認識するとき」には問題が生じるとしている。ただし、複合取引が同一契約書であってもその区分が適正に管理され、各々の金額の内訳が明らかな場合は、「契約上の対価を適切に分解して収益認識を行う」とした。
■取引の実態が透明性を増せば、価格決定メカニズムも変貌する 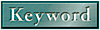 | | 財務会計基準機構 | | | 2001年7月に基本金10億円で設立された。米国のエンロン社やワールドコム社による不正経理問題をきっかけに日本企業の国際競争力強化を目的に、公正妥当な会計基準の見直しに係る調査や提言を行っている。
今回の草案は昨年7月に設置されたソフトウェア取引等収益専門委員会(西川郁生委員長)がまとめたもので、ITサービス業界からはNTTデータ、TIS、情報サービス産業協会が委員として参加した。同機構の規定は公認会計士の指針となるほか、商法や証券取引法が定める「準拠すべき標準規約」となる。 | | |
新会計基準は、平成18年4月1日以後開始する事業年度から適用されることになっている(1年間の猶予期間が設けられている)。いずれにせよ今回の草案は、ソフト産業の収益構造にメスを入れることになる。
経済産業省の特定サービス産業実態調査【情報サービス産業】によると、2004年度の同産業の売上高規模は約14兆5270億円。総売上高を就業者数で割った1人当たりの売上高は2551万円となり、実態と大きくかい離している。しかも主要取引先業種として「同業者」が1兆9309億円、全体の13.3%を占め、「金融業」となっていても銀行の情報システム子会社からの受注であるケースも少なくない。新会計基準の適用により、見せかけの産業規模が実態に近いものになるだろう。
もう一つ重要なのは、今回の指針に「ソフトウェアは無形の資産」と明記されたこと。これまでソフト開発の対価は「人件費+管理費」をベースとする人月単価で積算され、発注者は「経費」で処理することが多かった。しかし今回、公認会計士や金融機関代表で組織する財務会計基準機構が「資産」と明記した意味は大きい。
ソフト取引における多重構造の弊害(代金未払いや安易な要員派遣、不安定な雇用、価格設定の曖昧さなど)を健全化し、併せて人月単価積算方式から価値評価の価格決定メカニズムへの転換や受発注契約の明確化を促すことになる。


















