第三次AIブームでSASの価値を再認識
──Viyaは「AIプラットフォーム」とも謳われていますね。
AIについては、必ずしもViyaだけの機能ということではないんです。
──どういうことでしょうか。
SASはアナリティクスを愚直にみつめ続けてきましたから、実は最近のAIブームには多少懐疑的なところがありました。回帰分析のアルゴリズムというのは、要は機械学習であり、広義ではAIの範疇になる。しかし、われわれはそれをAIとは呼んでこなかったという感覚があるんです。Viyaに限らず、SASは昔から広義のAIの機能はずっと実装しているし、ユーザーもそれを活用してきたわけです。
私自身、学生時代の研究テーマはエキスパートシステムで、まさに1980年代後半の第二次AIブームの最中にいました。その後、ブームは瞬く間に去り、AI研究者は不遇の時代を過ごし、いまようやく第三次AIブームがきた。しかし、昔からAIをやっていた人間にとっては、そんなこと昔からやっていたよということも多いんですね。
一方で、ここまでAIという言葉が浸透したんだから、われわれも使ったほうがいいんじゃないかという議論も出てきた。
──マーケティング戦略としてはAIブームを利用したほうがいいと。
そうです。第三次AIブームは、ちゃんと成果を生むようなユースケースが出てきているのが第二次ブームとは違うところです。それを踏まえれば、広義のAIをポジティブに捉えてもいいのかなということで宗旨替えした感じですね。SASがやってきたことの価値をユーザーに再認識してもらえる機会でもあると考えています。
──SASは大企業向けビジネスに特化しているイメージでしたが、近年はパートナーと協業しつつ中堅・中小企業向けビジネスも拡大していますね。
SASは大企業向け、そして高いという話ですね(笑)。私は社長に就任した直後、さらなる成長のためのエンジンとして、中堅・中小ユーザーの開拓を掲げて、専門チームを編成しました。おかげさまで順調に立ち上がっているところです。アナリティクスというのは攻めのIT投資であり、SASの製品を活用してお客様が得られるビジネスバリューを考えれば、中堅・中小企業にとっても決して高い投資ではないと思っています。デジタルイノベーションのコアとなるパートナーとしてSASを認識してくれる日本企業をどんどん増やしていきたいですね。
 SASのビジネスモデルは、いたるところに
SASのビジネスモデルは、いたるところに
経営理念や創業者の意志、哲学が埋め込まれている<“KEY PERSON”の愛用品>アナログ×デジタルの三点セット
モレスキンの手帳、モンブランのペン、そしてiPadを常に携帯している。手帳は、革の質感も気に入っている。ペンは2006年にメルボルンで購入したモンブランの創業100周年記念モデル。プレゼンはiPadの出番で、PCは使わないという。
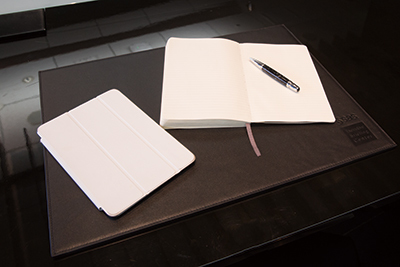

眼光紙背 ~取材を終えて~
アクセンチュア時代は、クライアントの売り上げを向上させ、ビジネスを成長させることがミッションだった。このコンサルティングの経験と、前職SAPジャパンでのパッケージソフトのビジネスの知見をうまくミックスして、SAS Institute Japanの成長をリードしてきた。
SASに自らがフィットしていると自負する。その根底には、創業者であるジム・グッドナイト氏への心からの共感があるようだ。現職就任にあたっての面接時、IoTなどの新しいトレンドにSASとしてどう向き合うべきか意見交換し、堀田社長は「オープン、エンド・トゥ・エンド、リアルタイムの方向にSASも行くべき」と話したという。当時すでに開発中だったViyaなどの製品がその後リリースされ、同じ方向を向いていたことを再認識することになった。「だからこの2年間はとてもエキサイティングだったし、本格的に日本の市場で拡販を進めるこれからのビジネスが楽しみで仕方がない」。(霹)
プロフィール
堀田徹哉
(ほった てつや)
1963年生まれ。大阪市出身。京都大学工学部卒業。米スタンフォード大学大学院経営工学修士課程、建設管理工学修士課程修了。国内事業会社で都市インフラ建設プロジェクトのプロジェクトマネジメントなどに従事した後、98年にアクセンチュア戦略グループに転職。通信業、ハイテク製造業、小売業などの事業戦略、経営改革、IT 戦略システム開発プロジェクトに携わる。2002年、同社エグゼクティブパートナーに。13年、バイスプレジデントとしてSAP ジャパンに入社し、アナリティクス、データベース、モバイルなどのプラットフォーム事業やプリセールス、インダストリーソリューション部門を担当。15年10月から現職。
会社紹介
米SAS Instituteは、アナリティクス・ソフトウェアのリーディングカンパニー。1976年の創業以来、連続して増収増益を続けており、2016年の売上高は32億ドル。グローバルでは金融、製薬などを中心に8万社を超える導入実績がある。未上場のプライベートカンパニーとして経営を続けているのも特徴。日本法人であるSAS Institute Japanは85年に設立され、1500社2300サイトの導入実績がある。
※週刊BCN1702号紙面上で、米SAS Instituteの2016年売上高の通貨単位に誤りがあ
りました。正しくは32億ドルです。お詫びして訂正いたします。

