遠隔指示・作業支援・可視化 三つのキーワードで迫る
スマートフォンやタブレット端末がそうであったように、ウェアラブル端末が一般に普及する頃には、ビジネスシーンでも欠かせない存在になることが予想される。国内でも、そうした時代を先読みした動きがみられるようになってきた。

日立グループのカード型のビジネス顕微鏡(上)と腕時計型のライフ顕微鏡 ウェアラブル端末のキーワードとして挙げた「可視化」については、日立グループが意欲的に取り組んでいる。グーグルやアップルの技術こそ使っていないが、日立製作所の中央研究所が中心となって独自に「ライフ顕微鏡」と「ビジネス顕微鏡」というウェアラブル端末を開発してきた。この二つは、同研究所が長年にわたって電子顕微鏡を研究してきたことに由来したネーミングになっていて、「目に見えないものを見えるようにする」(日立製作所中央研究所の渡邊純一郎・社会情報システム研究部主任研究員)という“可視化”を狙ったものだ。

日立製作所中央研究所の渡邊純一郎主任研究員(左)と日立システムズの栗山裕之主任研究員 ライフ顕微鏡は、腕時計型ウェアラブル端末に加速度センサなどを組み込んだもので、睡眠や安静、デスクワーク、軽作業、運動などを測定する。いわゆる“ライフログ”的なものであり、同社が独自に開発した可視化技術「ライフタペストリー」(図参照)によって、その人の生活習慣を可視化するものだ。一方、ビジネス顕微鏡は、社員証のような名札型のウェアラブル端末で、首にかけて使う。各種センサによって、誰と誰がどこで会って、どのくらいの時間にわたって話をしたのかなどを記録。組織の人間関係や活発度を可視化するものだ。
●組織の可視化ツールで威力 ビジネス顕微鏡は、これまで経験的、感覚的にしかわからなかった事象の可視化に成功している。例えば、M&A(企業の合併・買収)や組織再編で複数の会社や組織が統合したとする。旧会社や旧組織の従業員がどのようにコミュニケーションを図っているのかを可視化し、当初の計画通りに融合が進んでいるのかを測定するというものだ。首からさげた社員証型の端末には、赤外線や加速度、社内のどこにいるのかを測定するビーコンなどのセンサを組み合わせて、コミュニケーションの量や質を測定する。
電話でセールスをするアウトバウンド型のコンタクトセンターでの事例では、組織の「活発度」と「受注率」に有意な差があることを証明している。「活発度」とは休憩時間などでスタッフ同士が活発にコミュニケーションしているかどうかで、活発であれば「受注率」が上がるというものだ。事例によっては2割ほど受注率が上がったケースもある。コミュニケーションの内容は、他愛もない世間話でも十分で、内容よりも、むしろ「和やかな雰囲気」(渡邊主任研究員)が大切だという。
「受注が好調なのでコミュニケーションが促進されたわけではない」ことを証明するため、同じコンタクトセンターで二つのグループをつくり、一つはできるだけ同じ年齢の人同士で一緒に休憩をとってもらい、コミュニケーションを促進。もう一つは休憩時間を意識的にずらしたり、わざと年齢差が大きいグループで休憩をとってもらったりするなどによって、コミュニケーションを意図的に阻害したところ、やはり前者の「活発度」が高いグループで受注率が上がった。業務や組織改革のツールとしてウェアラブル端末を活用している事例である。
先述のライフログをベースとしたライフ顕微鏡は、日立グループ内で「生活習慣改善支援」に活用している。折しも、従業員50人以上の事業所で、医師や保健師などによってメンタルヘルス検査を義務化する「ストレスチェック制度」が2015年以降に実施されることが決まっていて、ライフ顕微鏡は、従業員のメンタルヘルスの増進にも役立ちそうだ。事業を担当する日立システムズの栗山裕之・事業開発センタ主任研究員は、「生活習慣病の改善やメンタルヘルスの増進、高齢者介護、スポーツなどさまざまな用途で事業化を推し進める」としていて、向こう1・2年で年商10億円規模のビジネスに育てていくことを計画している。
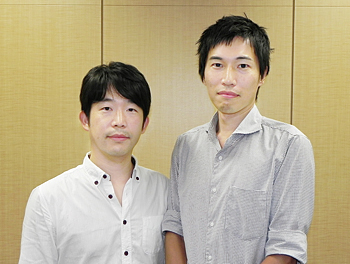
NTTデータMSEの杉本哲朗課長代理(左)と山下智也課長代理 NTTデータMSEも、「遠隔指示」「作業支援」 「可視化」をキーワードにウェアラブル端末の事業化を推進している。同社は眼鏡型ウェアラブル端末を使って管理者から作業者への「遠隔指示」、カメラでバーコードを読み取ることによる「作業支援」、顔認識による人物の「可視化」に取り組む。例えば、バーコードを読み取ることによって、 「この商品は××です。○○へ運んでください」とメッセージを表示して作業ミスを減らしたり、保守作業などで現地の作業員に「次の作業は××です。現場の写真を送ってください」と遠隔で指示を出したりする。顔認識では、セミナーの来場者の顔を認識して、眼鏡型ウェアラブル端末にプロフィールを表示する機能を想定している。
NTTデータMSEは、すでに複数の実証実験を行っていて「今年度(2015年3月期)末までには実証実験の数が10件を超える」(杉本哲朗・ソリューション企画担当課長代理)と、実ビジネスに向けて着々と歩を進めている。
また、NTTデータMSEは、今年7月、ウェアラブル端末上で動作する業務アプリケーションと、ウェアラブル端末を管理するシステムなどをコンポーネント化した「Bizウェアラブル」を発表した。「ウェアラブル端末を最短2週間で導入できる」(山下智也・ソリューション企画担当課長代理)ように、サービスをメニュー化するなどの取り組みによって、向こう3年で30億円規模のビジネスに育てていく方針だ。
今さら聞けないウェアラブル端末
ウェアラブル端末(ウェアラブルコンピュータ)は、身につけるコンピュータである。古くは歩数計や多機能デジタル時計なども、ある種のウェアラブル端末といえなくもないが、現在は狭義にはアップルやグーグルの技術の流れをくむデバイスを指す。腕時計型のウェアラブル端末向けのOS「Android Wear」では、サムスンやLG、モトローラ・モビリティなどが製品化に取り組んでいて、この9月にはアップルが「Apple Watch」を発表している。
スマートフォンと密接に連動することから、スマートフォンの補助端末と捉えることもできる。FacebookやLINEのメッセージ通知をウェアラブル端末に表示することで、いちいちカバンからスマートフォンを取り出さなくても情報が得られる。かつてスマートフォンが普及したとき、「パソコンの画面を見る回数が大幅に減った」という話をよく聞いたが、ウェアラブル端末の登場によって、今度は「スマートフォンの画面を見る回数が減少する」ことが予想される。
ウェアラブル端末の形態は、大きく分けて腕時計型や眼鏡型、体のどこかに装着するタイプ(腕輪型、ネックレス型、ヘッドセット型など)の三つ。メジャーなのは腕時計型と眼鏡型だろう。両目を覆って没入感を重視したヘッドマウントディスプレイ(HMD)は、拡張現実(AR)などで活用が進むものの、現状のHMDを身につけたまま動き回るのは困難なことから、日常的に装着して作業が可能なウェアラブル端末とはいい難い。記者の眼
グーグル、アップル派か B2B専用として独自に開発か
ウェアラブル端末は文字通り身につける端末なので、ファッション性やフィット感、使い勝手のよさが強く求められる。この点は、ポケットやカバンに入れるスマートフォンよりも格段にシビアだ。今、注目を集めているアップルやグーグルなどのウェアラブル端末はコンシューマを強く意識したものであり、こうした市販品がビジネスでそのまま使えるとは限らない。
さまざまな実証実験で事業化のめどをつけたのち、業種・業務に特化したウェアラブル端末を何らかのかたちで開発することが望ましい。日立製作所は「顕微鏡シリーズ」をすでに自社で開発している。近年では台湾のEMS(製造受託サービス)メーカーが小ロットでのカスタマイズ対応能力を高めていることから、メーカーではないSIerでも独自のハードウェアを開発しやすくなった。
アップルやグーグルが巨額の予算を投じて開発したウェアラブル端末と、その背後にある彼らのクラウドサービスを組み合わせてビジネス領域へ展開するのも一つの手段ではある。だが、ウェアラブル端末の市場がまだ黎明期だからこそ、独自に開発するのも有力な選択肢にしておきたいところだ。


