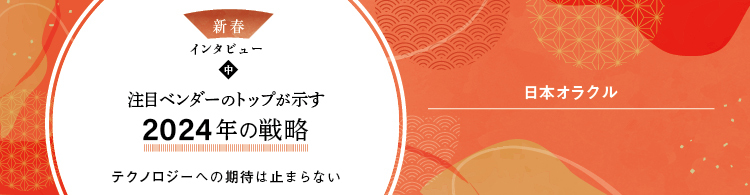――2023年を振り返るとどうか。
景気の不透明感や地政学的リスクから発生するセキュリティインシデントを踏まえ、ITをもう一度見直そうというお客様が増えてきた。DXの流れで、新しい分野への投資は盛り上がったが、今の業務を支えている仕組みに対しての投資はおざなりになっていたのではないか。
 取締役執行役社長 三澤智光
取締役執行役社長 三澤智光
例えば個人情報が漏えいしたとして、その理由は、OSにパッチを当てていなかったり、データベースが古いままであったりする。調べると、基幹システムまで同じ状態だったということもある。(顧客の中で)「レジリエンスの向上」というテーマが広がってきた。そういった課題解決を手伝うことが増えた年だったといえる。
――その課題解決の手法としてクラウドを第1候補に挙げる企業は増えてきたか。
クラウドというと、シェアリングエコノミーのコンピューティング環境、つまりパブリッククラウドが一般的だ。ただ、そういう話ではなく、クラウドコンピューティング環境で実装されているテクノロジーを使いたいお客様は増えている。パブリック、最近では「Newオンプレミス」という言い方もあるが、場所は問わず、今の仕組みをモダナイズするために、次世代のプラットフォームで実装したいということだ。
生成AIを支えるデータ基盤が重要に
――23年は生成AIが大きなトレンドとなった。今後の展望は。
オラクルは競合より速くて安いGPU環境を提供して生成AI開発を支えているが、日本ではそのお客様はあまりいないとみる。ただ、私たちメーカー自身が、AIを生成・ファインチューニングし、ソフトウェアの中に埋め込む動きはさらに広がる。メーカーがリードする生成AI市場は間違いなくある。
自社のデータを活用したAIを導入したいお客様も、もちろんいる。一般企業が生成AIを使う場合はRAG(外部データベースなどからデータを取得し、回答の精度を高める技術)の仕組みで実装することが当たり前になるだろう。生成AIを支えるデータが重要になり、データプラットフォームをどうデザインするかという議論が求められる。パブリッククラウド上にデータを置きたくないと考えるお客様も出てくるはずで、そのニーズに応えられる点が、大きな差別化ポイントになると考えている。
――24年の抱負を。
今期掲げた「日本のためのクラウドを提供」しかない。プラットフォームやアプリケーションのレジリエンス担保は日本のためになる。また、エンタープライズ企業が生成AIを使う最初の年になるので、最初の一歩をどうお手伝いするかにも取り組まなければならない。自社のビジネスについては楽観的に考えている。デマンドがあり、競争力も圧倒的にあるからだ。