
ITビジネス情報誌
最新号 2026年01月26日付 vol.2090
SPECIAL FEATURE
[特集]新春インタビュー(下) 注目ベンダーのトップが示す2...
vol.1825
2020/05/22 09:00
日本が誇るSIer。これまではアベノミクスや東京五輪などの影響でユーザー企業の投資意欲が強く、人手不足が深刻になるほど多くのSI案件が動いていた。しかし、新型コロナウイルスの感染拡大による未曾有の経済危機の可能性も指摘される中、次の一手をどうするべきかを早急に考えなければならない状況となった。SIerのトップに改めて“SI論”を問う。

vol.1803
2019/12/11 09:00
業務システムが古くなると保守性が悪くなり、IT予算を圧迫する大きな一因となる。全てを作り直すか、必要なところだけ切り出して残りは塩漬けにするか、といった解決の選択肢に加え古いシステムの内部を可視化して保守性を改善する手法もある。
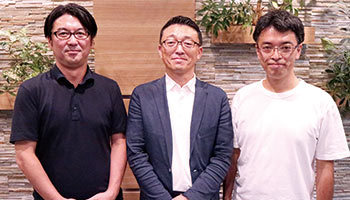
vol.1802
2019/12/04 09:00
アクロホールディングス(小野賀津雄・代表取締役CEO)は、非常にユニークなグループ経営をしているSIerである。昨年度(2018年12月期)連結売上高は145億円で、中堅規模にもかかわらず、決算上の連結子会社は27社、過半数出資などで連結対象になり得る会社までを含めると36社の大所帯。
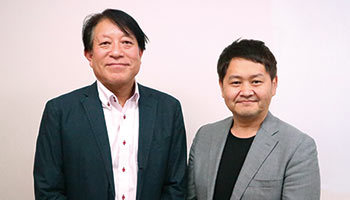
vol.134
2019/08/14 09:00
エイチ・ピー・エスは、客先常駐でのソフト開発や受託ソフト開発で伸びてきた会社だ。「客先常駐はSEの頭数で売り上げの上限が決まったり、受注環境の悪化の影響を受けやすいなどのデメリットがある一方、さまざまな顧客のITシステムの構築経験を積んで、自社の強みを形成していくのに役立つメリットもある」と、三上智親代表取締役は指摘する。
![<SI論 システム開発はどう変わるのか>[第134回]エイチ・ピー・エス 客先常駐で経験を積み強みの形成につなげる](https://d1gt4pceznpvut.cloudfront.net/files/topics/168907_ext_03_0.jpg?v=1565073304)
vol.133
2019/07/10 09:00
セントラル情報センターは、組み込みソフトや業務アプリケーション、通信系のシステム開発などを幅広く手掛けるSIerだ。大手ITベンダーからの仕事に加えて、独自ビジネスの拡大にも力を入れており、「バランスのとれた収益構造」(長谷川武之社長)を強みとしている。
![<SI論 システム開発はどう変わるのか>[第133回]セントラル情報センター 景気変動に強いビジネスモデルを構築](https://d1gt4pceznpvut.cloudfront.net/files/topics/168327_ext_03_0.jpg?v=1562046172)
vol.132
2019/04/10 09:00
エヌデーデーは、病院や公益といった社会インフラに強いSIerだ。コンピューターメーカーや大手SIerがひしめく社会インフラ領域にあって、長年にわたってエンドユーザーとの直接取引を重視。大きな景気の変動が起こると、下請けSIerが次々と契約を切られていく中、元請け比率の高いエヌデーデーは粘り強く勝ち残ってきた。
![<SI論 システム開発はどう変わるのか>[第132回]エヌデーデー 大きなプロジェクトの小さな歯車にはならない](https://d1gt4pceznpvut.cloudfront.net/files/topics/167026_ext_03_0.jpg?v=1554183658)
vol.131
2019/04/03 09:00
利用した分の料金を支払うサブスクリプション方式のサービスが、さまざまな分野で増加傾向にある。特にIT業界は、クラウドサービスの普及という後押しもあって、それが顕著だ。
![<SI論 システム開発はどう変わるのか>[第131回]BBF 30年間で辞めた社員はたった3人!](https://d1gt4pceznpvut.cloudfront.net/files/topics/166873_ext_03_0.jpg?v=1553576978)
vol.130
2019/03/20 09:00
「SIにおいて『納品して終わり』は損をしている」が、スカイの河村正史代表取締役の持論である。導入した業務アプリケーションによって、「ユーザー企業がしっかりと業績を伸ばせるよう支えるほうがビジネスとしては重要」だと説く。
![<SI論 システム開発はどう変わるのか>[第130回]スカイ 納品してからがビジネスの本番](https://d1gt4pceznpvut.cloudfront.net/files/topics/166701_ext_03_0.jpg?v=1552372579)
vol.129
2018/12/26 09:00
組み込みソフトはメーカー向けの仕事ばかりではない――。日新システムズでは、組み込みソフト開発で培った技術を生かし、エネルギー管理システム(EMS)の制御用デバイスやIoT向け無線ネットワークなどの独自商材を開発。
![<SI論 システム開発はどう変わるのか>[第129回]日新システムズ 組み込み技術をスマートコミュニティーに応用](https://d1gt4pceznpvut.cloudfront.net/files/topics/165598_ext_03_0.jpg?v=1545112766)
vol.128
2018/12/19 09:00
組み込みソフト開発を得意とするアックスは、小型軽量なAIや自動運転のソフトウェア開発の領域で強みを発揮している。
![<SI論 システム開発はどう変わるのか>[第128回]アックス 高度技術者が活躍できる場を増やす](https://d1gt4pceznpvut.cloudfront.net/files/topics/165498_ext_03_0.jpg?v=1544508243)